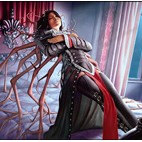注意:MtG用語でDMについて書きます。
さて、Duel Mastersのデッキでも作ろうかな。
フォーマットは殿堂構築(2019年8月末デュエルマスターズ殿堂準拠)。
まったく環境知らないし、デッキの作り方も忘れた。
何でも、環境にはMtGの《ならず者の精製屋》をはるかに超えた性能を持つ生物がいるとか。
めちゃくちゃだよ。手札が減らずにマナが増え、墓地も肥えるカードが3マナ生物とはこれいかに。そもそも、こういう新しいカードは今どきの人が使いこなせているから、復帰したての自分が何言ってもそれには及ばない。ここは、このゲーム構造から攻めて使うカードを決めるべきだ。
このデュエルマスターズというゲームはMtGとは違って第2メイン、戦闘後メインフェイズというものが存在しない。つまり、戦闘によって与えられたシールドは対戦相手の手札となって、アドバンテージを与えてしまうことになる。もちろん、そのターンでケリをつけてしまえば相手のアドバンテージなんて関係ないわけです。まあ、そんなこと許されるわけないよなあ。《無双竜機ボルバルザーク》、お前のことだよ。
MtGプレイヤー用に能力語解説すると、
スピードアタッカー:速攻。Haste。
W・ブレイカー:シールドを2枚破る。
このDMでは、初期シールド5枚とプレイヤー自身へのアタック、計6回のアタックでゲームが決まる。つまり、こいつは強いんです。
はい。気を取り直すと、自分にはそうそう戦闘による勝利は見込めないですね。相手ターンでの干渉手段が少ないので、ハンドアドバンテージを盤面に還元されてしまうとそのまま負けてしまうかもしれません。
同じ理由でメガハンデスが候補から消えます。当然ですね。
ということは、戦闘以外での勝利、つまりコンボやロックに頼らざるを得ません。
次回は各種コンボ、ロックを見ていきます。ではでは。
さて、Duel Mastersのデッキでも作ろうかな。
フォーマットは殿堂構築(2019年8月末デュエルマスターズ殿堂準拠)。
まったく環境知らないし、デッキの作り方も忘れた。
何でも、環境にはMtGの《ならず者の精製屋》をはるかに超えた性能を持つ生物がいるとか。
天災 デドダム P 水/闇/自然文明 (3)
クリーチャー:トリニティ・コマンド/侵略者 3000
このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、自分の山札の上から3枚を見る。そのうちの1枚を自分の手札に加え、1枚をマナゾーンに置き、残りの1枚を墓地に置く。
めちゃくちゃだよ。手札が減らずにマナが増え、墓地も肥えるカードが3マナ生物とはこれいかに。そもそも、こういう新しいカードは今どきの人が使いこなせているから、復帰したての自分が何言ってもそれには及ばない。ここは、このゲーム構造から攻めて使うカードを決めるべきだ。
このデュエルマスターズというゲームはMtGとは違って第2メイン、戦闘後メインフェイズというものが存在しない。つまり、戦闘によって与えられたシールドは対戦相手の手札となって、アドバンテージを与えてしまうことになる。もちろん、そのターンでケリをつけてしまえば相手のアドバンテージなんて関係ないわけです。まあ、そんなこと許されるわけないよなあ。《無双竜機ボルバルザーク》、お前のことだよ。
無双竜機ボルバルザーク VR 火/自然文明 (7)
クリーチャー:アーマード・ドラゴン/アース・ドラゴン 6000
このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、他のパワー6000のクリーチャーをすべて破壊する。その後、このターンの後にもう一度自分のターンを行う。そのターンの終わりに、自分はゲームに負ける。
スピードアタッカー
W・ブレイカー
※プレミアム殿堂
MtGプレイヤー用に能力語解説すると、
スピードアタッカー:速攻。Haste。
W・ブレイカー:シールドを2枚破る。
このDMでは、初期シールド5枚とプレイヤー自身へのアタック、計6回のアタックでゲームが決まる。つまり、こいつは強いんです。
はい。気を取り直すと、自分にはそうそう戦闘による勝利は見込めないですね。相手ターンでの干渉手段が少ないので、ハンドアドバンテージを盤面に還元されてしまうとそのまま負けてしまうかもしれません。
同じ理由でメガハンデスが候補から消えます。当然ですね。
ということは、戦闘以外での勝利、つまりコンボやロックに頼らざるを得ません。
次回は各種コンボ、ロックを見ていきます。ではでは。
[Duel Masters]カイシャク備忘録その1―思い出語り
2019年8月30日 デュエル・マスターズ最近、デュエル・マスターズ(Duel Masters:DM)に復帰したので、いろいろ思う所を書いていこうかと。
まず、自分のカードゲーム遍歴とそこから考えられるデッキ構築論を少々。
最初に触れたカードゲームは、小学生の頃の『デュエル・マスターズ』でした。使っていたのは、闇文明(MtGでは黒)ですね。レアなんてパックから当たったもの1枚しかないから、いっぱいのコモン・アンコモンにちょっとのレア、って感じでした。好きだったのは、除去とライブラリーアウト。
当時の地元は、小学生は『デュエル・マスターズ』で、中学生は『遊戯王』という風潮でしたが、自分はずっとDM。これで中学時代にとあるアーキタイプを好きになります。「ランデス」です。これだとコモン・アンコモンでもレアいっぱいのデッキにそこそこ勝てるわけですね。
そこから、ある程度たって、カードゲームを離れるわけですが、『Magic : the Gathering』を始めます。これが面白いゲームでのめり込みました。また、カードゲームの元祖ということもあり、カードゲームについてもいろいろと学びました。
ここで初めてカードゲームにてデッキを組む、ということをちゃんと考えたわけです。それまでは「持っている好きなカードを使う」、に対しここから「環境、メタゲームというものを理解して、そこに勝てるデッキを使う」になったわけです。まあ、実際MtGの大きな大会で結果を出しているわけではないですが、モチベーションはそうです。DMの「ランデス」も環境にランデス対策が少ない、というメタ読みはしてましたが、今ほどではありません。
さて、なんでDMに帰ってきたか。それはMtGで培ったデッキ作成能力、プレイングを昔好きだったカードに試したい、ということです。MtGでは、「大抵どんなカードでも完全上位互換は存在しない」ということを学びました。それはきっとDMでも同じはず。当時使っていたカードを4枚投入してデッキを組みたいわけです。メタゲーム云々言っておいて、結局は使いたいカードがある、という感じですね。
復帰のモチベーションはそこでしたが、ではデッキ構築の際に目指すところはと言いますと、それは大会上位入賞ですね。つまりメタゲーム的に勝てるデッキを作る、ということです。
DMには100人~300人規模の店舗大会であるCSや2000人規模の国内GPが設定されているので、その辺はMtGと引けを取らない、わけですね。
構築論はかなりMtGに偏ってしまうかと思いますが、頑張って作っていこうかと。
自分語りの文章はもういいか。ではでは。
まず、自分のカードゲーム遍歴とそこから考えられるデッキ構築論を少々。
最初に触れたカードゲームは、小学生の頃の『デュエル・マスターズ』でした。使っていたのは、闇文明(MtGでは黒)ですね。レアなんてパックから当たったもの1枚しかないから、いっぱいのコモン・アンコモンにちょっとのレア、って感じでした。好きだったのは、除去とライブラリーアウト。
当時の地元は、小学生は『デュエル・マスターズ』で、中学生は『遊戯王』という風潮でしたが、自分はずっとDM。これで中学時代にとあるアーキタイプを好きになります。「ランデス」です。これだとコモン・アンコモンでもレアいっぱいのデッキにそこそこ勝てるわけですね。
そこから、ある程度たって、カードゲームを離れるわけですが、『Magic : the Gathering』を始めます。これが面白いゲームでのめり込みました。また、カードゲームの元祖ということもあり、カードゲームについてもいろいろと学びました。
ここで初めてカードゲームにてデッキを組む、ということをちゃんと考えたわけです。それまでは「持っている好きなカードを使う」、に対しここから「環境、メタゲームというものを理解して、そこに勝てるデッキを使う」になったわけです。まあ、実際MtGの大きな大会で結果を出しているわけではないですが、モチベーションはそうです。DMの「ランデス」も環境にランデス対策が少ない、というメタ読みはしてましたが、今ほどではありません。
さて、なんでDMに帰ってきたか。それはMtGで培ったデッキ作成能力、プレイングを昔好きだったカードに試したい、ということです。MtGでは、「大抵どんなカードでも完全上位互換は存在しない」ということを学びました。それはきっとDMでも同じはず。当時使っていたカードを4枚投入してデッキを組みたいわけです。メタゲーム云々言っておいて、結局は使いたいカードがある、という感じですね。
復帰のモチベーションはそこでしたが、ではデッキ構築の際に目指すところはと言いますと、それは大会上位入賞ですね。つまりメタゲーム的に勝てるデッキを作る、ということです。
DMには100人~300人規模の店舗大会であるCSや2000人規模の国内GPが設定されているので、その辺はMtGと引けを取らない、わけですね。
構築論はかなりMtGに偏ってしまうかと思いますが、頑張って作っていこうかと。
自分語りの文章はもういいか。ではでは。